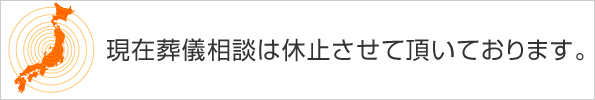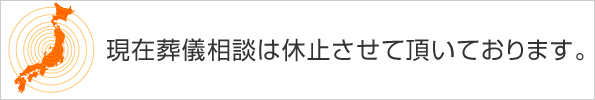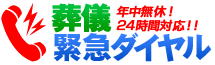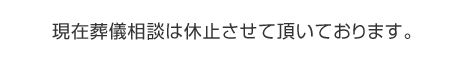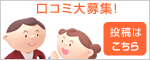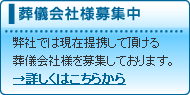葬儀の意味
葬儀の意味- 葬儀をする意味とは?
なぜ葬儀を行うのでしょう?
葬儀の意味と葬儀を行う理由についてご説明します。
通過儀礼
生まれてすぐ行われる命名から、
お宮参り、七五三、入学、卒業、就職、成人式、結婚、出産、還暦など、
人はその人生の中でいくつもの通過儀礼を経験することになります。
そして一番最後の通過儀礼が葬儀であると考えられます。
その人の人生の最期に区切りをつける通過儀礼として、お葬式はなくてはならないものなのです。
死亡届の提出などの手続きによって、それまで社会の中で生きてきた人がいなくなったということを公知させますが、 それだけでなく、その人の人生に区切りをつける。
そんな通過儀礼としての側面としても、葬儀はなくてはならないものです。
命の尊さを学ぶ
人は生きていて、そして死んでしまいます。
しかし自分がいつかは死ぬものとわかっていても、
自分の死を自分では理解・経験することができません。他人の死から経験するだけです。
最近、人の死や人の命というものを大事なものだと理解できず、
軽視する子供が増えてきて問題になっています。
現代ではそう実感する機会はほとんどなくなってしましたが、古代では人々は集団で居住し、
その中で互いに助け合わなければ日々を生き抜くのはとても大変なことでした。
ですので人の命は尊いものだと認識することは習慣となり、
その尊いものがなくなった時には儀式が行われていて、
実際4万年以上も前のネアンデルタール人のものとされる墓も見つかっています。
人の命がとても大事なものであるという認識がなければ、互いに助け合うこともできません。
そのため、葬儀という儀式を通じて、人の命の尊さを再確認していたのだと考えられています。
残された人の悲しみを癒す
親族、友人、知人。ほとんどの人は誰かしらの葬儀に参列したことがある、
もしくは、することになります。そして家族や親友など、その関係が親しければ親しいほど、
その死を受け入ることは難しく、悲しみを乗り越えるのにも時間がかかります。
そんな中悲しみを他の人と共有したり、悲しいときに人の優しさに触れたりすることで癒されることがあります。
昔は村八分でも葬儀の際には周囲が手伝ってくれましたし、
今も葬儀ではたくさんの親戚や地域の方が手伝いをしてくれます。
近しい人を亡くした悲しみに直面し、その悲しみを癒すため。
心に折り合いをつけ、しっかり処理していくため。
そして人の温かさに触れることで沈みがちな気持ちを和らげるため、
葬儀があると考えることもできます。
死者の霊を慰める
古来より、霊の存在というのは民間に強く信じられてきました。
恨みや無念、未練などそういう感情は死者をこの世にひきとどめ、
それがときに災厄や病気の原因であると考えられていた時代もあったのです。
そんな時、人々はその霊を慰め、安らかな眠りにつけるよう祈りを捧げてきました。
葬儀には死者を無事天国に送り届けるという、文化的、宗教的な役割もあります。