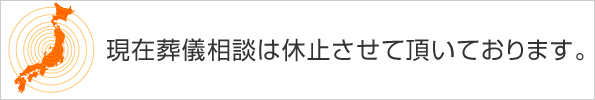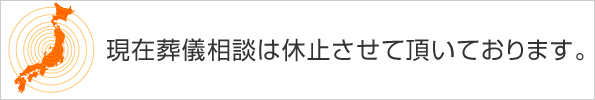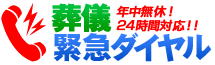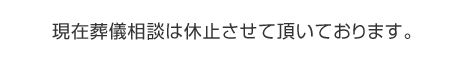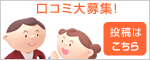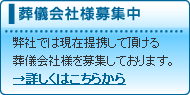葬儀の司会
葬儀の司会- 葬儀の司会の手際のよさで葬儀はそのよしあしが決まってしまうと
いっても言い過ぎではありません。
突然葬儀の司会を頼まれても困らないよう、葬儀の司会の役割と
段取りについてご説明いたします。
司会の役割
通夜や葬儀の席での進行を取り仕切り、重要な役割を果たす司会。
司会がいなければ通夜や葬儀はスムーズに運びません。
葬儀社やセレモニーホールでの通夜や葬儀が増えたことにより、
最近では、葬儀社の担当者やプロによる司会も一般的になってきました。
彼らプロは式の進行を熟知し、その場にふさわしい言葉遣いで丁寧に通夜や葬儀などを進行してくれます。
その一方で、自宅で通夜や葬儀を行う場合は、親族から依頼された世話係が司会の役割を果たします。
この場合、当然司会は素人であることがほとんどなので、
事前に葬儀社や僧侶と念入りな打ち合わせが必要になります。
しかし身内や近所の方が進行する、手作りで堅苦しくない、
何とも言えないしみじみとした雰囲気の葬儀というのも好まれます。
司会進行の手順
自宅で葬儀の司会をする場合、どのような手順になるのか。またどのようなことに気をつければよいのでしょう。
進行についてしっかり確認し、使用する言葉遣いやマナーなどについてご紹介します。
開式前
参列者に着席していただくようアナウンスします。
僧侶の入場
僧侶は通常、司会のアナウンスとともに入場します。
「導師様の入場です」
など礼を失しない言葉を選びましょう。
開式
「ただ今より、○○家の葬儀を開式いたします」
という司会の言葉で、式が始まります。
葬儀の手順としては僧侶の読経、弔辞、焼香の順になります。
宗派ごとに細かい違いもありますので、ここでは解説などしないほうが無難です。
弔辞
遺族がお願いしていた方が、弔辞を読みます。
「ここで〜様より、ご弔辞を賜ります」という紹介に、故人との関係を付け加える程度で問題ありません。
弔電の披露
「ご弔電を賜っておりますので、ご紹介します」
弔辞の後、届いている弔電を読み上げます。
葬儀前の打ち合わせによりますが、僧侶の退場後でも問題ないでしょう。
焼香
弔辞(もしくは弔電の披露)の後、遺族、一般参列者の順で焼香を誘導します。
なお、この時指名焼香がある場合があります。
「〜様よりご焼香を賜ります」
と一般参列者より前にお願いします。
導師退場
一般参列者の焼香が終わると、
「導師様が退場されます」
の言葉で僧侶が退場します。
供花
遺族、親族を中心に、故人への最後のお別れをしていただきます。
花などを手向けるように案内します。
出棺
「それでは出棺です」
という司会に言葉とともに近親者で棺を運び出します。
以上が信仰の手順になります。
進行の際に注意すべきことですが、
葬儀を執り行うのは司会者ではなくあくまで導師です。
司会者がでしゃばって葬儀を取り仕切ったり、余計な言葉を長々と言い連ねたりしてはいけません。
打ち合わせや導師の指示のもと、シンプルな進行を心がけましょう。