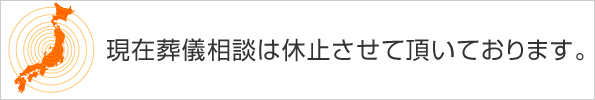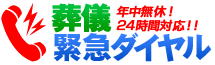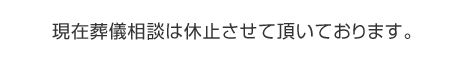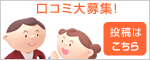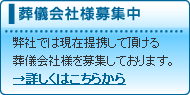- ‘’‹V‚ج—¬‚ê
- ‘’‹V‚جڈ€”ُ
- ’ت–é
- ‘’‹VپEچگ•تژ®
- ‰خ‘’پEٹزچœ–@—v
- ‘’‹V‚ج‚¨•ش‚µ
- –@—vپE‹ں—{
- ‘’‹VŒم‚جڈ”ژ葱‚«
- ˆâژY‘ٹ‘±
- گi’»ƒ`ƒFƒbƒNƒVپ[ƒg
- ‘’‹V‚جŒ`ژ®
- •§ژ®‘’‹V‚جŒ`ژ®
- گ_ژ®‘’‹V‚جŒ`ژ®
- ƒLƒٹƒXƒg‹³ژ®‘’‹V‚جŒ`ژ®
- –³ڈ@‹³ژ®‘’‹V‚جŒ`ژ®
- ‘’‹V‚جƒ}ƒiپ[
- •§ژ®‘’‹V‚جƒ}ƒiپ[
- گ_ژ®‘’‹V‚جƒ}ƒiپ[
- ƒLƒٹƒXƒg‹³ژ®‘’‹V‚جƒ}ƒiپ[
- ژQ—ٌژز‚جƒ}ƒiپ[
- ˆâ‘°‚جƒ}ƒiپ[
-
‘’‹V‚ج‘O‚ج–éپAŒجگl‚جگ¬•§‚ً‹F‚é‹Vژ®‚ً’ت–é‚ئ‚¢‚¢‚ـ‚·پB
Œ»چف‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚جڈêچ‡”¼–é‚إچs‚ي‚êپA‚»‚جژèڈ‡‚ة‚à’èŒ^‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB
‚»‚±‚إ’ت–é‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚²گà–¾‚µ‚ـ‚·پB
’ت–é‚ج—¬‚êپi•§ژ®‚جڈêچ‡پj
ژ©‘î‚ب‚ا‚ةˆہ’u‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ب‚çپAˆâ‘ج‚ًگ´‚ك‚ث‚خ‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
‘ج‚ًگ@‚‚ظ‚©پA’jگ«‚ب‚ç‚خ’ن“پ‚ً‚ ‚ؤپAڈ—گ«‚ب‚炨‚µ‚ë‚¢‚ًژ{‚µ‚ـ‚·پB
‘’‹Vژذ‚ھŒˆ‚ـ‚ء‚½‚ç‚ـ‚¸چإڈ‰‚ة‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚±‚ئ‚إ‚·پB
‡@ژَ•tٹJژn’ت–éٹJژnژٹش‚ج‚¨‚و‚»30•ھ‘O‚©‚çژَ•t‚ًٹJژn‚µ‚ـ‚·پB‡A’¢–â‹q‚جژَ•t’¢–â‚ة–K‚ꂽ•û‚ة–F–¼’ ‚ض‚ج‚²‹L’ ‚ً‚¨ٹè‚¢‚µ‚ـ‚·پB
‘rژهپEˆâ‘°‚حپA’¢–âژٹش‘ر‚إ‚àŒجگl‚جˆâ‘ج‚ج‘¤‚©‚ç—£‚ꂸپAڈoŒ}‚¦‚〈‘—‚è‚ح‚µ‚ـ‚¹‚ٌپB
’¢–â‹q‚ة‚حˆâ‘ج‚ج–T‚ç‚©‚ç•ش—炵‚ـ‚·پB‡B‘m—µ‚ج‘—Œ}‘m—µ‚ج“’…‚ة‚حپAگ¢کb–ً‚ھ‰‘خ‚µپA
‘إ‚؟چ‡‚ي‚¹‚ًچs‚¢‚ـ‚·پB
’ت–é‚جٹJژn‘O‚ئ“اŒoŒم‚ح•تژ؛‚ة‚ؤ’ƒ‰ظ‚إ‚à‚ؤ‚ب‚µ‚ـ‚·پB‡C’ت–é‚جٹJژn‘m—µ‚ھ“üڈꂵپA’ت–é‚ھژn‚ـ‚è‚ـ‚·پB
‘m—µ‚ح“üڈêŒم“اŒo‚ًچs‚¢پA
“اŒo‚جژٹش‚ح‚¨‚و‚»30•ھ‚ظ‚ا‚إ‚·پB‡D’¢ژ«‘m—µ‚ج“اŒoŒمپA‚ ‚ç‚©‚¶‚ك‚¨ٹè‚¢‚µ‚ؤ‚¢‚½•û‚ة’¢ژ«‚ً“ا‚فڈم‚°‚ؤ‚à‚ç‚¢‚ـ‚·پB‡Eڈؤچپ‘m—µ‚جژwژ¦‚ةڈ]‚¢پA‘rژهپAˆâ‘°پA‹كگeژزپA—FگlپE’mگl‚ب‚ا‚جڈ‡‚إˆê‚آ‚جچپکF‚²‚ئ‚ة1گl‚¸‚آڈؤچپ‚ً‚µ‚ـ‚·پB‡F‘m—µ‘قڈêڈؤچپ‚ھڈI‚ي‚é‚ئ‘m—µ‚ھ‘قڈꂵ‚ـ‚·پB‡G‘rژه‚جˆ¥ژA‘m—µ‘قڈêŒمپA‘rژه‚ھˆâ‘°پB‹كگeژز‚ً‘م•\‚µ‚ؤˆ¥ژA‚ًچs‚¢‚ـ‚·پB‡H’ت–é‚ش‚é‚ـ‚¢ڈؤچپ‚جڈI‚ي‚ء‚½’¢–â‹q‚ً•تژ؛‚ةˆؤ“à‚µپA
’ت–é‚ش‚é‚ـ‚¢‚ً‚µ‚ـ‚·پB
’ت–é‚ش‚é‚ـ‚¢‚ج‰‘خ‚àپAˆâ‘°‚إ‚ح‚ب‚گ¢کb–ً‚â‘’‹Vژذ‚جگl‚ھچs‚¢‚ـ‚·پB‡I‰ï‘’—çڈَ‚ً“n‚·’¢–â‹q‚ھ‹A‚ç‚ê‚é‚ئ‚«‚ةپA‰ï‘’—çڈَ‚ً“n‚µ‚ـ‚·پB
‰ï‘’—çڈَ‚ة‚ح’تڈيپAگ´‚ك‚ج‰–‚ب‚ا‚ھ“ü‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‡J–鉾‹كگeژز‚ھŒً‘م‚إŒجگl‚ئˆê–é‚ً–¾‚©‚µپAƒچƒEƒ\ƒN‚âگüچپ‚ج‰خ‚ھگ₦‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚µ‚ـ‚·پB
پ¦‚±‚ê‚ç‚ح‚ ‚‚ـ‚إˆê”ت“I‚ب—ل‚إ‚·‚ج‚إپA’nˆو‚جڈKٹµ‚â•—ڈK‚ة‚و‚ء‚ؤ‘½ڈˆل‚¢‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB
’ت–é‚جگبژں
’ت–é‚جچغ‚جگبژں‚حپAچص’d‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ‰E‰œ‚©‚ç‘rژهپAˆâ‘°پA‹كگeژز‚جڈ‡‚ة‚ب‚èپA
چ¶‰œ‚ة‚حگ¢کb–ً‘م•\‚ھچہ‚èپA’mگl—FگlپAŒجگl‚ج‰ïژذٹضŒWژز‚ئ‚¢‚¤Œ`‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
Œجگl‚ج—Fگl’mگlپA‰ïژذٹضŒWژز‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حچׂ©‚‚±‚¾‚ي‚炸پA“üڈêڈ‡‚ةچہ‚ء‚ؤ‚à‚ç‚¢‚ـ‚·پB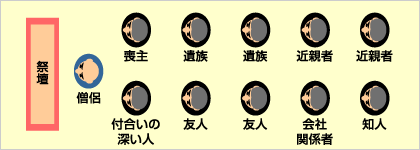
گ¢کb–ً‚جژdژ–
‘rژهپAˆâ‘°‚â‹كگeژز‚حŒجگl‚جˆâ‘ج‚ج‘¤‚©‚ç—£‚ê‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB ‚»‚±‚إپA’¢–â‹q‚ض‚ج‘خ‰‚â‚»‚ج‘¼ژGژ–‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAگ¢کb–ً‚ھˆâ‘°‚ة‚ب‚è‚©‚ي‚ء‚ؤچs‚ء‚ؤ‚‚ê‚ـ‚·پB
گ¢کb–ً‚جژه‚بژdژ–
پ@‰ïŒvپFچپ“T‚ًچپ“T’ ‚ة‹L“ü‚·‚éپB
پ@ژَ•tپF’¢–â‹q‚ج–¼‘OپAچپ“TپA‹ں‚¦•¨‚ً‹L’ ‚µپA‚»‚ꂼ‚ê‚جŒW‚ة•i•¨‚ً“n‚·پB
پ@Œg‘ر•iپF‰؛‘«‚âژè‰×•¨‚ً—a‚©‚èپA‹A‚èچغ‚ة“n‚·پB‹A‚é‹q‚ةˆ¥ژA‚ً‚·‚éپB
پ@‰ïڈêپF‘m—µپAˆâ‘°‚ًگب‚ةˆؤ“à‚â‰ش—ض‚جگف’u‚ًچs‚¤پB
پ@گع‘زپF‘m—µ‚ض‚ج’ƒ‰ظژq‚ج—pˆسپB’ت–é‚ش‚é‚ـ‚¢‚جگع‘ز‚ب‚اپB
پ@‘نڈٹپF‚¨’ƒپAژً‚ج—pˆسپB’ت–é‚ش‚é‚ـ‚¢‚ً‚آ‚‚éپi—؟—‚ب‚ا‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح’چ•¶‚جڈêچ‡‚à‚ ‚éپjپB
پ@گiچsپF‘’‹V‚جگiچs‚âˆâ‘°‚â‘’‹Vژذ‚ئ‚جژ–‘O‚جگiچs‘إ‚؟چ‡‚ي‚¹پB
پ@’“ژشپFژش‚ً’“ژشڈê‚ض‚ج—U“±‚ئ‹A‚è‚جŒؤ‚رڈo‚µپB
-