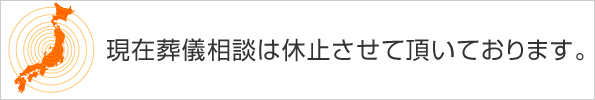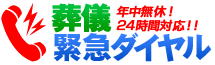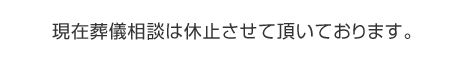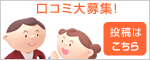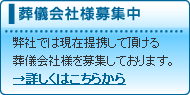|
死後7日目に行われ、葬儀後一番最初に行われる供養です。
|
|
|
| 死後14日目に行われる法要です。通常近親者のみで行い、僧侶を招くかお寺に出向いて読経してもらいます。 |
|
|
| 死後21日目に行われる法要です。通常近親者のみで行い、僧侶を招くかお寺に出向いて読経してもらいます。 |
|
|
| 死後28日目に行われる法要です。通常近親者のみで行い、僧侶を招くかお寺に出向いて読経してもらいます。 |
|
|
死後35日目に行われる法要です。通常近親者のみで行い、僧侶を招くかお寺に出向いて読経してもらいます。
浄土真宗では、この日に納骨を行う場合が多いです。 |
|
六七日(むなのか) |
| 死後42日目に行われる法要です。通常近親者のみで行い、僧侶を招くかお寺に出向いて読経してもらいます。 |
|
四十九日。七七日(しちしちにち) |
死後49日目に行われる法要です。
四十九日には遺骨を埋葬するので、日時・場所を決めて寺院と打ち合わせをします(会葬者が出席しやすい土日が多い)。 |
|
|
|
|
| 満1年の法要です。自宅、菩提寺あるいは斎場で近親者、親族で供養し、僧侶に読経をしてもらいます。なお、この日までが喪中で一周忌をもって喪明けとします。 |
|
|
| 満2年の法要です。自宅、菩提寺あるいは斎場で近親者、親族で供養し、僧侶に読経をしてもらいます。 |
|
|
| 満6年の法要です。自宅、菩提寺あるいは斎場で近親者、親族で供養し、僧侶に読経をしてもらいます。 |
|
|
| 満12年の法要です。自宅、菩提寺あるいは斎場で近親者、親族で供養し、僧侶に読経をしてもらいます。 |
|
一七回忌 |
満16年の法要です。自宅、菩提寺あるいは斎場で近親者、親族で供養し、僧侶に読経をしてもらいます。 |
三十三回忌 |
満32年の法要です。自宅、菩提寺あるいは斎場で近親者、親族で供養し、僧侶に読経をしてもらいます。以後は永代供養をする場合が多いです。 |
五十回忌 |
満49年の法要です。 |
百回忌 |
満99年の法要です。 |